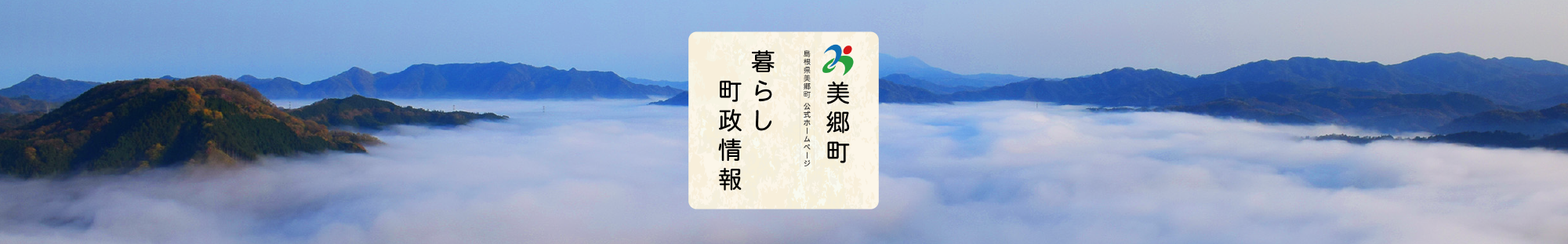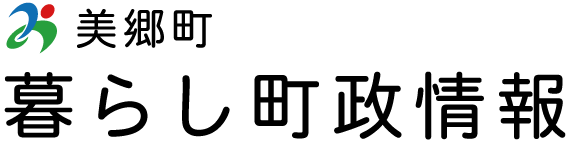国民健康保険税
国民健康保険税の概要
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入されている方にかかる税金です。
国保税は世帯主に課税されます(世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主となります。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます)。
国保税は、加入者皆さんが病気やけがをしたときなどの医療費等に充てられる大切な財源です。必ず納期限内に納めましょう。
国民健康保険税の計算方法(令和6年度)
国民健康保険税は被保険者数、被保険者の前年中の所得、保険税率等を使って計算します。計算は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(注1)からなり、3分野の合算額が年税額となります。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
|
所得割 (課税所得金額(注2)×税率) |
8.25% | 2.90% | 2.40% |
|
均等割 (被保険者1人あたり) |
25,000円 | 8,300円 | 6,900円 |
|
平等割 (1世帯につき) |
17,300円 | 6,600円 | 5,200円 |
| 賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
・年度の途中で加入、脱退した場合は加入月数に応じて保険税を計算します。
・国民健康保険税は加入の届出日ではなく、国民健康保険の資格を取得した日までさかのぼって保険税を納めていただきます。
・職場の保険に加入された等で国保の該当でなくなった場合は、必ず国保の資格喪失の届出が必要です(お手続きがない限り、国保税もかかり続けます)。
注1 介護納付金分のみ40歳~65歳の方が対象。
注2 課税所得金額は総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額
国民健康保険税の納め方
〇普通徴収
・口座振替:毎月月末に(月末が土日祝日の場合、翌月曜日)引き落としします。
※対象の金融機関…ゆうちょ銀行、山陰合同銀行、島根県農業協同組合、島根県中央信用金庫。
※口座振替のお手続きはご希望の金融機関の窓口にてお願いいたします。
・納付書 :各金融機関の窓口、役場会計課、大和事務所、各交流センター、コンビニ、スマホ決済等。
〇年金特別徴収
年金の支給日に引き去りします。ただし年金から引き去りするには以下の条件があります。
・世帯主が国民健康保険に加入している。
・世帯主以外の被保険者が全員65歳以上
・世帯主の介護保険料が特別徴収であること。
・「特別徴収対象年金」が18万円以上であること。
・介護保険料と国民健康保険料の合算額が「特別徴収対象年金額」の2分の1以下であること。
暫定期間と本算定期間
・美郷町の国民健康保険税は12期(4月から翌年3月)に分けてお支払いいただきます。
・前年の所得、及びその年度の保険税率が確定するまでの4月~6月(特別徴収の場合4月~8月)を仮算定期間、7月~翌年3月(特別徴収の場合10月~2月)までを本算定期間としておりますのでご注意ください。
〇普通徴収の場合
| 仮算定期間 | 本算定期間 | ||||||
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ・・・ | 第12期 |
| (4月) | (5月) | (6月) | (7月) | (8月) | (9月) | (3月) | |
| 計算に必要な前年中の所得・保険税率が未確定のため、前年度の国民健康保険税額を用いて仮算定した額(前年度の金額を1/12)を6月までお支払いいただきます。 | 決定した前年中の所得・保険税率を用いて本算定をした年税額から、仮算定期間にお支払いいただいた税額を差し引きし、残りの月数で割って算出されたひと月分の税額を7月から毎月お支払いいただきます。 | ||||||
仮算定の計算日(4月上旬)以降に国民健康保険への加入手続きをされた場合、仮算定期間のお支払いはありません。支払い開始は本算定を行った7月からとなります(世帯に追加で加入の場合も税額の変更は7月から)。
〇特別徴収の場合
| 仮算定期間 | 本算定期間 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 前年度2月の保険税額と同額を年金から引き去りします。 | 決定した前年中の所得・保険税率を用いて本算定をした年税額から、仮算定期間にお支払いいただいた税額を差し引いた残りの金額を10月以降の年金月に引き去りします。 | ||||
国民健康保険税の軽減(申請不要)
(ア)低所得者軽減
国民健康保険の世帯主、及びその世帯に属する被保険者の合算した軽減判定所得が次のような場合には、下記の通り減額されます。
| 軽減判定基準額 | 減額される額 | ||||||
| 43万円+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下 | 均等割・平等割が7割減額 | ||||||
| 43万円+{(29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(注1))}+{10万円×(給与所得者等の数ー1}以下 | 均等割・平等割が5割減額 | ||||||
| 43万円+{(54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下 | 均等割・平等割が2割減額 | ||||||
注1:国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場 合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
(イ)特定世帯にかかる平等割を軽減(後期移行経過措置)
同じ世帯の国民健康保険被保険者が、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険被保険者が単身世帯となるとき、医療保険分(基礎賦課額)と後期高齢者医療支援金分の平等割を、当初5年間(注2)は1/2、6年目以降(注3)の3年間は1/4軽減します。
注2:この期間の世帯を特定世帯といいます。
注3:この期間の世帯を特定継続世帯といいます。
(ウ)未就学児の均等割軽減
未就学児の均等割は通常の1/2となります。
低所得者軽減がすでにかかっている場合は低所得者軽減後の金額を1/2とします。
国民健康保険税の減免(申請必要) ※納期限の7日前までに申請をしてください。
(ア)旧被扶養者減免(後期移行にともなう激変緩和措置)
被用者保険(社会保険や船員保険、共済保険など)の被保険者本人が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行した場合、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険に加入することになります。
これらの方は、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険に加入したことで保険税を負担することになるため、世帯主にかかる負担が激増しないようにするために申請により保険税を減免することができます。
| 区分 | 減免額 |
| 旧被扶養者の所得割 |
全額 |
| 旧被扶養者の均等割 | 半額(ほかの軽減と合わせて半額を限度) |
| 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割 | 半額 |
(イ)非自発的失業者減免
会社を自己都合以外で退職し、職業安定所が発行する「雇用保険受給資格者証」の離職理由が【11,12,21,22,23,31,32,33,34】の場合、申請により給与所得を30/100として保険税を計算します。
(ウ)産前産後減免
国民健康保険にご加入で、出産予定・及びすでに出産された被保険者の方は、出産(予定)月の1か月前から、出産(予定)月の2ヶ月後までの4か月間の所得割・均等割全額が減免されます。
申請は出産予定の6か月前から可能です。
(エ)その他
・災害等による減免
・拘禁中の減免等
・その他特別の事情により国民健康保険税が支払えなくなった場合は申請により減免を受けられる場合があります。ただし減免の適用には審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
国民健康保険税の納付が困難になった場合は住民課税務係までご相談ください。