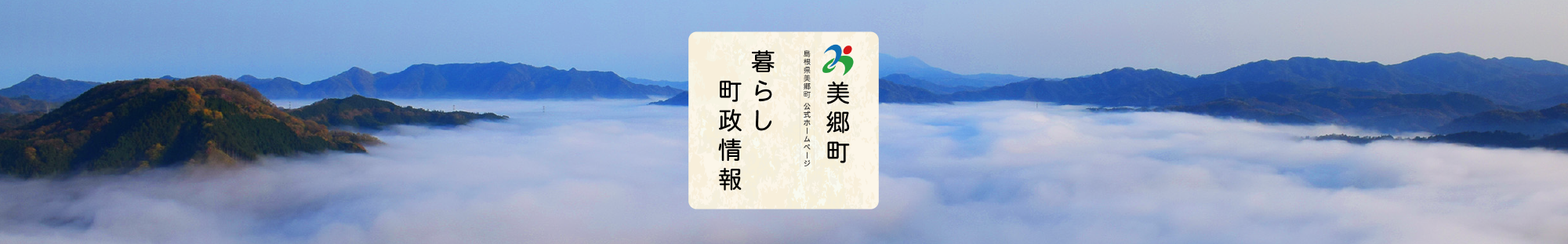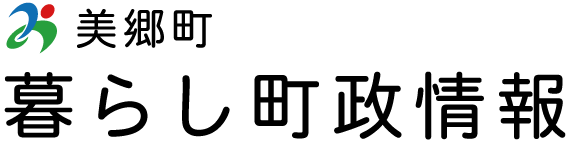令和8年度(令和7年分) 所得の申告相談(所得税・町県民税等)について
2026年01月20日
今年も所得の申告相談を2月16日(月)から3月16日(月)までの期間で開催します。申告書類をすべて整えて、漏れのないようご留意ください。
日時および会場は下記添付PDFファイルのとおりです。
![]() 「令和8年度(令和7年分)申告相談日程表」をダウンロードする(PDF:70kB)
「令和8年度(令和7年分)申告相談日程表」をダウンロードする(PDF:70kB)
町県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ県や町の仕事のための費用を、住民の方がその負担能力(所得)に応じて分担し合うという性格の税金です。申告の必要な皆さんが自ら所得を申告し、所得に応じた税負担をしていただくことは、課税の公平性を維持するために重要なものです。申告期限内に正しい申告を済まされますようお願いします。
申告相談は予約制です
申告相談は、全日程予約制で実施します。予約は、インターネットまたは電話で行います。
予約の開始日時は、1月26日(月)8:30です。インターネットは24時間受付、電話は平日8:30~17:15まで受け付けます。予約は、前日までにお済ませください。
会場に来られる方が家族の申告も一緒に行う場合は、一つの予約枠を予約してください。申告書を作成する人数分の予約枠を予約しないようご注意ください。
予約をしていない方は、当日会場に来ていただいても受け付けできませんので、必ず事前に予約をしてください。
インターネット予約はこちら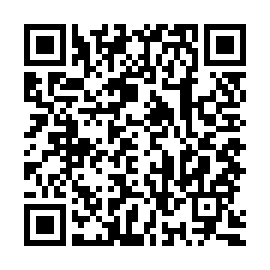
電話予約は住民課(電話番号0855-75-1213)まで
※美郷町公式LINEのリンクからも予約できます。
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、美郷町に住所があり、令和7年中に所得(収入)がある方は申告が必要です。
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がある方
・給与所得者で給与以外の所得がある方、または2カ所以上から給与を受けた方
・給与所得者で年末調整を受けなかった方(中途退職された方など)
・給与所得者で、年末調整では控除できない医療費控除を受ける方など
公的年金を受給されている方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金の源泉徴収票に記載されていない次の各種控除を受ける方は町県民税の申告が必要です。
・年金天引き以外で支払った社会保険料(国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等)がある方
・生命保険料や地震保険料を支払った方
・配偶者や扶養親族の控除をする方
・本人または控除対象配偶者、扶養親族が障がい者手帳をお持ちの方
・寡婦もしくはひとり親の方(ひとり親は扶養親族である子がいる場合)
・医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除をする方など
次に該当する方は所得(収入)がなくても町県民税の申告をお願いします。
・児童手当等の各種手当または給付金を受ける方や、国民年金の免除申請をする方
・所得証明書や非課税証明書が必要な方(会社の社会保険の被扶養者になっている方など)
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方など
※所得が一定額以下の場合、国民健康保険税等の軽減措置の適用がありますが、申告がないと軽減措置を受けることができません。
申告に必要なもの
・本人確認書類
【マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)+身元確認書類(運転免許証など)】
※控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者についても、マイナンバーの記載が必要です。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
・給与・公的年金等の令和7年分の源泉徴収票や、事業所得に伴う支払調書(コピー不可)
※源泉徴収票を紛失した場合は、申告までに給与や年金の支払者に再発行してもらってください。
・収支内訳書(事業所得(営業、農業、不動産)がある方)
・各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・個人年金保険料・各種社会保険料など)
・障がい者手帳または障がい者控除対象者認定書(本人または家族で障がい者控除の適用を受ける方)
・申告者本人の預金通帳(所得税の還付を受ける方や、新規に口座振替を申込む方)
・利用者識別番号(番号の交付を受けていない方で町の相談会場に来場された方は、会場にて電子申告に必要な利用者識別番号を取得していただきます。)
※町の申告会場で過去に番号を取得されている方は、すでに番号の登録が済んでいますので必要ありません。
・国や地方公共団体からの助成金について個別の事実関係によって課税となるものがありますので関係書類をご持参ください。(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金などについては非課税となります。)
注意事項
領収書などはあらかじめ自宅で集計するなどして、相談時間の短縮にご協力ください。申告に必要な書類が揃っていないと、正しい税額を計算することができません。日頃から必要書類の整理・保管を心がけましょう。
なお、発熱やせき等の症状がある場合には、来場を控えるなど、感染予防・感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
事業所得(営業・農業)、不動産所得
・収支計算の基礎となる領収書・帳簿などを必ず整理記帳して、お持ちください。
※収入や経費等を記帳していない方は、ご自身で計算した後に申告相談を受けていただくことになります。
・作成した帳簿は7年間、請求書や納品書、領収書等の書類は5年間保存してください。
事前に郵送等で農業申告書の提出をされていない場合は、下記申告書を参考に収支をまとめた上で申告会場へお越しください(任意の様式をお使いいただいても構いません)。
医療費控除
・支払った医療費の領収書は、個人別・医療機関別に分け事前に集計し明細書を作成してきてください。
・対象となる領収書は令和7年中に支払った分です(領収印の日付を確認してください)。例えば、12月分の入院費用を令和8年1月になってから支払った領収書は、今回の申告には含みません。
・老人施設等の介護保険サービスに対する費用を医療費控除とする場合は、必ず「医療費控除の対象となる金額」が明記された領収書をお持ちください(施設に医療費控除用の領収書を発行してもらってください)。
・医療費に対して補てんされた金額(高額医療費や医療保険金等)がある場合は、その金額が分かるようにしてきてください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
令和7年中に入居し、初めて控除を受ける方は下記の書類が必要です。(令和6年6月30日までに建築された住宅と、7月1日以降に建築された住宅では取扱いが異なります。)
1.登記事項証明書または登記簿謄(抄)本
2.請負契約書(売買契約書)の写し
3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
※増改築や中古住宅、認定長期優良住宅について控除を受ける際は、更に各種証明書が必要です。
・住宅の建築にあたって補助金の交付を受けた場合は、その金額が分かるようにしてきてください。
・土地についても住宅借入金等特別控除を受ける場合は、土地についての1、2も必要です。
・2年目以降も申告により住宅借入金等特別控除を受ける方(農業や自営業の方、年末調整がお済みでない方)は、3の年末残高証明書と税務署から発行される住宅借入金等特別控除申告書をご持参ください。
収用等により資産を譲渡した場合の特別控除の特例
公共事業施行者の収用などにより、土地・建物などの資産を譲渡した場合で特別控除の特例を受ける方は、下記の書類が必要です。
1.公共事業施行者が交付した各種証明書(買取り等の申出証明書、買取り等の証明書など)
2.契約書(土地、建物、移転補償)
3.移転補償等に基づき支出した内容が分かる領収書
その他
・ご自身で申告書を作成できる方は、完成した申告書を申告会場に持参するか、広島国税局業務センター出雲分室に直接提出してください。広島国税局業務センター出雲分室へは郵送で提出することもできます(今回から提出先が変更となりました)。
※郵送先 〒693-8689 出雲市塩冶善行町13番地3 出雲地方合同庁舎 広島国税局業務センター出雲分室
・申告書の作成は、国税庁ホームページの便利な「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。申告書を印刷し書面で提出するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)のどちらかを選ぶことができます。
※e-Taxを利用するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを用意するか、税務署が発行した電子申告用IDとパスワードが必要です。